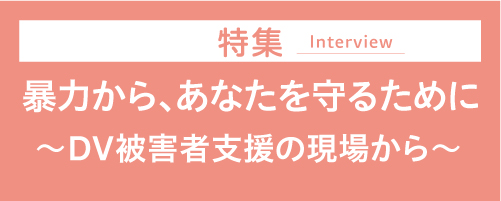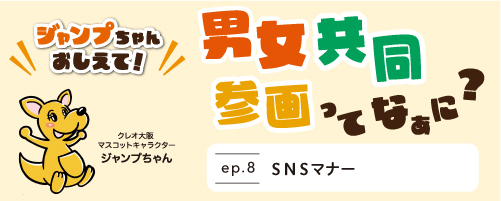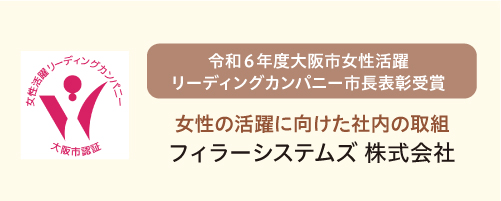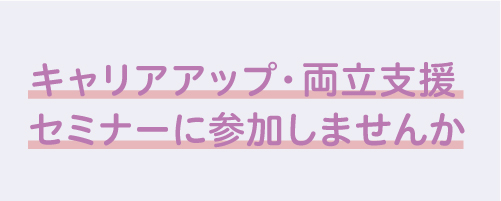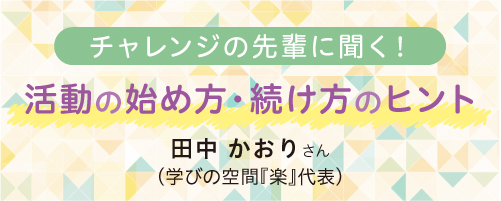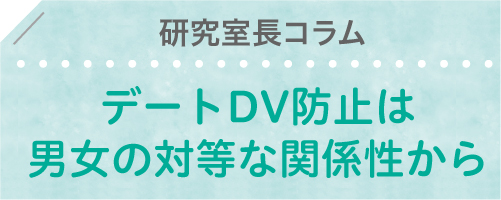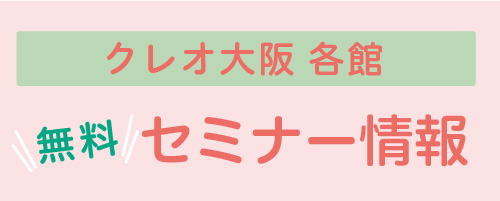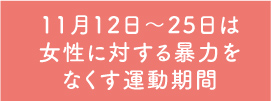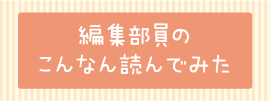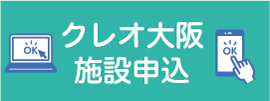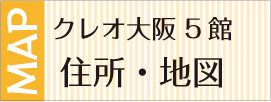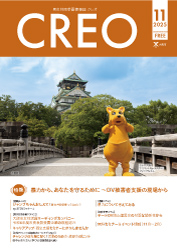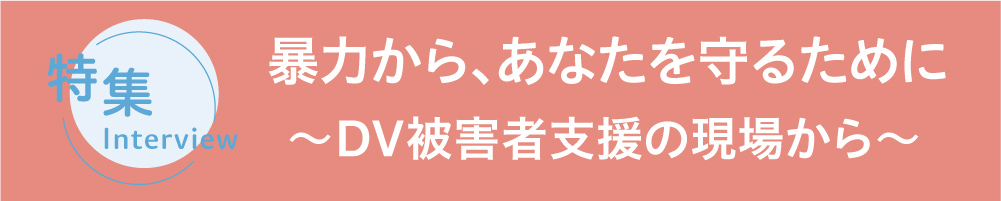
法律や支援の体制整備が進む一方で、女性たちは今もさまざまな困難を抱えています。長年にわたり、DV(ドメスティック・バイオレンス)や離婚問題に向き合い、多くの相談に耳を傾け、寄り添ってこられた、弁護士の億智栄(おくちえ)さんにDVの現状や支援のあり方についてお話を伺いました。

DV被害者支援を通して、見えてきたこと
ー弁護士としてのこれまでの歩みや、支援への思いについてお聞かせください。
平成12(2000)年に弁護士登録をして、今年でちょうど25年になります。平成11(1999)年に男女共同参画社会基本法、平成13(2001)年に配偶者暴力防止法(※1)が施行され、私の弁護士としてのスタートと法律の大きな転換点が重なっていました。当時は「そんな法律があるんだ」くらいの受け止め方でしたが、仕事を続ける中で、これらの法律は多くの女性たちの長年の運動や尽力の積み重ねによって生まれたのだと実感するようになりました。DVや離婚といった経験は、生活や心に深く影響を及ぼす出来事ですが、暮らしを見つめ直し、新しい一歩を踏み出すきっかけにもなります。そうした過程に携わりながら、相談者に寄り添った支援を続けることに大きな意義とやりがいを感じています。
※1 配偶者暴力防止法…正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」。配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的とする日本の法律で、「DV防止法」とも呼ばれる。
社会の変化が映す、暴力のかたち
ーDVの実態や傾向について教えてください。
時代とともに、暴力のかたちは複雑化しています。特に、経済力の差が背景にあるDVは今も根強く、「俺と同じくらい稼いでから言え」といった言葉は、いまだに聞かれます。家庭と仕事の両立を考え、あえてバランスが取れる働き方を選んでいる女性も多い中で、経済面での差を突きつけられ、黙り込んでしまう状況に追い込まれるのです。中には、辛さをSNSで吐き出すことで、気持ちを整理しようとする方もいますが、相手への嫌悪感が更に募り、かえって問題解決から遠ざかってしまう場合もあります。経済的圧迫と精神的な支配が絡み合うことで、状況はより複雑化し、多くの方が相談に至るまでに年単位で我慢を重ねています。「先週こんなことがあった」というよりも「もう限界」となった段階で、ようやく相談に来られるのです。女性から男性へのハラスメントももちろんありますが、経済的な格差を背景にすれば、やはり女性の被害が多いのが実情です。
ー精神的なDVやモラルハラスメント(※2)が増えているようですが、社会のどんなことが影響しているのでしょうか。
家族のかたちやライフスタイルの変化が背景にあるといえます。仕事と生活のバランスがとれた状態を「ワーク・ライフ・バランス」といいます。ここでいう「ライフ」とはプライベートの生活のことで、家事・育児や介護だけでなく、趣味や自己啓発、心身の健康などを含みます。しかし、実際にはこれらの「ライフ」で求められていることが、「やらなければいけないこと」になっていて、まるで「ワーク・〝ワーク″・バランス」と言った方が良いような状態になっていることも少なくありません。
仕事でも生活でも「ワーク」に追われた結果、パートナー間ですれ違いが多くなり、同居していてもコミュニケーションがうまくとれず、身体的な暴力はなくても、家庭内別居のような状態になることがあります。そして、それがDVやモラハラといった深刻な問題に発展する場合もみられます。
最近では、家事・育児に積極的な男性も増えましたが、一方で離婚や別居の際には、子どもの親権や養育に関する争いは、より複雑になっています。当事者や子どもたちの状況に寄り添いながら、長期的に支え続ける伴走型の支援が一層求められています。
※2:モラルハラスメント:言葉や態度による精神的な暴力・嫌がらせのこと。略して「モラハラ」とも呼ばれる。
寄り添う支援、支える支援
ーDV被害者のための今の制度や支援について、どう思われますか。
DV被害者を守る制度としては、配偶者暴力防止法に基づく保護命令があります。それに加えて、一時保護、シェルター、母子自立支援施設など、公的な支援機関との連携体制も整ってきています。ただ、実際には「暮らしを変えるのが怖い」、「子どもの通学区域を変えたくない」といった理由から、すぐに避難を選べない方も多くいます。
また、精神的DVやモラハラの場合は、命に関わる危険性が見えにくいため、ギリギリの状態でも生活を続けながら悩んでいる方も多くいます。現行の配偶者暴力防止法だけでは、こうした見えにくいDVへの対応が十分とは言い切れない点があります。ハローワーク、子ども家庭センター、住宅支援など、さまざまな機関が連携してサポートする体制が望まれます。今も一部ではそうした連携が進んでいますが、関係機関がよりスムーズにつながれるネットワークの必要性を強く感じます。
ー身近な人がDVを受けていると感じたらどうしたらよいですか。
「DVの被害にあっているのでは」と感じても、そのことを話すのは簡単ではありません。「それってDVじゃないの?」とそのまま伝えてしまうと、かえって心を閉ざされてしまうこともあります。大事なのは、「つらくない?」と優しく声をかけること。「話を聞くよ」というスタンスで寄り添い続けることが大切です。今じゃなくてもまた今度でもいい、話したくなったときに思い出してもらえたらいい。そっと寄り添う存在になれたら、きっとその人の助けになるでしょう。
DVには、被害者を社会から切り離し、孤立させる「社会的暴力」も含まれます。それが人とのつながりや、自ら考える力を奪っていき、支援を求める意欲さえ失わせてしまいます。だからこそ、周囲との関わりはとても大事です。つらいときに「あなたはひとりじゃない」と伝えることが大きな支えになるはずです。
相談することが、新しい一歩に
ー困難を抱える方が安心して相談できる場所や支援について教えてください。
大阪弁護士会には、様々な問題に親身に寄り添ってくれる弁護士がたくさんいます。「こんなことで相談してもいいのかな」と思われる方も多いのですが、悩みの大きさは人それぞれです。「ちょっとつらいな」、「誰かに話を聞いてもらいたいな」と思った時がそのタイミングかもしれません。話すことで状況が整理できたり、新しい選択肢に気づけることもあります。他にも、クレオ大阪の女性総合相談センターや配偶者暴力相談支援センター、男性の悩み相談、また、24時間受付をしている「DV相談+(プラス)」などでも相談できます。
相談に来られた方の中には、「自分には何もできない」と卑下する方も少なくありません。けれど実際には、家事や育児、家族の健康や生活の段取り、仕事までこなし、日々複数の役割を果たす力のある方ばかりです。その力や可能性が十分に発揮できていない状況を見ると残念でなりません。いざという時に立ち上がれる準備や、相談できるつながりを持っておくことは、自分自身を守る力になります。ひとりで抱え込まず、まずは話してみてください。

億 智栄さん(弁護士)
大阪弁護士会所属。同会人権擁護委員会7部会(両性の平等)委員。日本弁護士連合会性の平等委員会委員。平成12(2000)年10月に弁護士登録し、たまたまDV被害者のための法律相談を担当したことをきっかけに、以来、DV被害者の離婚事件を多く手掛ける。
11月12日~25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。
どのような理由であれ、暴力は決して許されるものではありません。
〈暴力には様々な種類があります。〉

無視をする、悪口を言う、みんなの前で恥ずかしい思いをさせるなど

たたく、なぐる、ける、物をなげつけるなど

仕事をやめさせる、デート代を払わせる、借りたお金を返さないなど

無理やりキスや性行為をする、わいせつな写真や動画を無理やり撮影するなど

メールなどをチェックする、交友関係を制限する、行動を監視・制限するなど
出典:大阪市男女共同参画普及啓発事業
DVに関するご相談は・・・
大阪市では、配偶者やパートナー等からの暴力のお悩みや不安について、相談をお受けしています。ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
相談先はこちら
2025年11月号 コンテンツ
発行:大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 編集:大阪市立男女共同参画センター中央館
指定管理者:大阪市男女共同参画推進事業体 (代表者:(一財)大阪男女いきいき財団)
クレオ大阪ホームページ