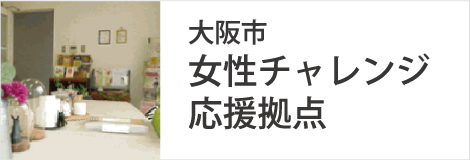大阪男女いきいき財団|自分らしくイキイキと輝ける社会へ。

インフォメーション
竹中恵美子さん(大阪公立大学名誉教授/元大阪市女性協会副理事長)追悼のことば
2025.07.09 NEWS大阪市立大学名誉教授の竹中恵美子さんが2025年7月1日に95歳で永眠されました。
労働問題をジェンダーの視点から捉える女性労働研究をパイオニアとして拓かれた方で、1996年から2010年までは、当財団の副理事長として、道を切り開く精神を示していただきました。
心からの感謝と哀悼の意を表して、謹んで、ここに多大なご功績の一部を紹介させていただきます。
竹中さんは1949年、戦後初めて女性にも門戸を開放した旧制大阪商科大学(現大阪公立大学)に進学されました(入学者は男性216人で女性は3人)。
そこで最初に学んだことが、当時の名和統一教授(国際経済学)の「経済学とは金儲けの学問ではない、経世済民の学である」という言葉と、イギリスの経済学者アルフレッド・マーシャルの「経済学を学ぶ者に必要なのは、<冷静な頭脳と温かい心情(Cool Head but Warm Heart)である >という言葉だったそうです。
「これらは砂地に水がしみこむように私の心をとらえた。このような経済学者との出会いが、男性本位の経済学の中で不問にされ、軽視され続けてきた女性労働問題に傾斜していく原因ともなったものと思う。」と語っています。
研究者としてのスタートは1952年の卒業と同時に、母校大阪市立大学(現大阪公立大学)経済学部助手就任からです。その後、講師を経て1974年に教授に。86年には国公立大学で女性初の経済学部長に就任されました。
しかし、1958年に出産してからは育児も担うため、家庭保育園(当時の大阪市の助成制度)や近所の方に保育を依頼するなどして、綱渡りの日々だったそうです。
研究時間は細切れの「細切れ時間研究者」であることへのいら立ち、辛さはどうしようもなく、(細切れではない)「全日制研究者」の彼らより5年長生きして元を取ろうと心をいさめたと語っています。(『竹中恵美子の女性労働研究50年』株式会社ドメス出版2009年より)。
1996年、当財団の副理事長に就任され、1997年3月の財団広報紙創刊号で、このように述べられています。
ジェンダー・ニュートラルな社会に向けて
~無償労働の評価~
無償労働の社会・経済的評価については、問題がないわけではありません。無償労働にかかわる時間を拾いだし、賃金換算をするとしても、換算する賃金を女性の平均的賃金とするか、パート賃金にするかによっても大きく異なり、いずれにせよ、ジェンダーに偏った評価にならざるを得ないでしょう。ジェンダー中立的な評価とは何か、その開発が問われているといえます。
しかしなにより重要なことは、無償労働の社会・経済的評価を行うことの社会的意味です。日本では一部に誤解があるようですが、それは専業主婦の主婦役割に対する経済的評価といったこととは無縁です。のみならず、たんに無償労働が経済的活動の一環であるという社会的認識を高めるというだけでなく、無償労働を主婦役割に囲い込むことによるマイナスを除去し、社会と男女両性に担い分けする方策を打ち出すことにあるのです。
~21世紀に向けての課題~
いま取り組む課題は、一方では、機会の平等を徹底させるために、「男女雇用機会均等法」を真に実効性あるものに見直すとともに、他方では、機会の平等が結果の平等に結びつくためのジェンダー・ニュートラルな社会をいかに作り上げるかにかかっています。つまりは、政策の単位を家族から個人に移行させ、女性が専ら担ってきた無償労働を、社会的に目に見える形にする社会保障・社会福祉制度を拡充し、社会・男女の新しい分担を構築していくことだといえるでしょう。この二つの課題を連動させていくことこそ、21世紀への課題です。21世紀を男女両性にとって、展望ある共生社会としうる鍵といいうるでしょう。
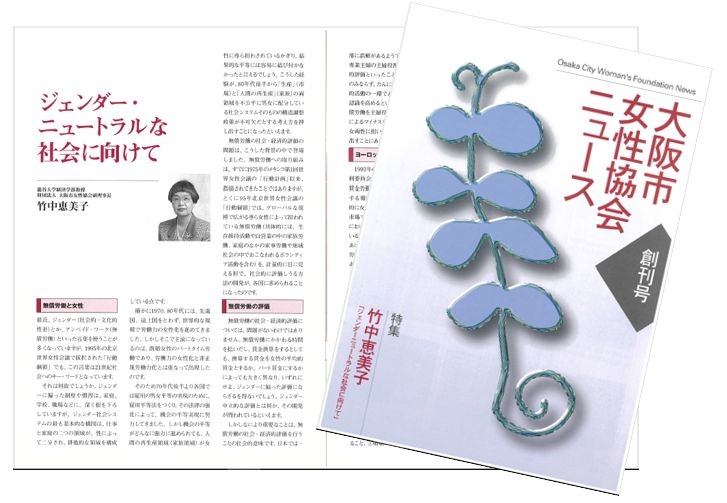
竹中さんのこうした指摘の延長線上で、1999年に男女共同参画社会基本法が施行されました。社会・男女の新しい分担の構築に関しては、ようやく2022年6月に国がまとめた女性版骨太の方針の中で、「もはや昭和の時代の想定が通用しない」として昭和の時代に作られた様々な制度・慣行・意識の構造的な課題解決の必要性に触れています。
それでも、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を含む固定的な性別役割分担意識はまだまだ根強く、賃金の男女格差も男性を100とした場合、女性は75.8と8割にも届いていません(厚生労働省「2024年賃金構造基本統計調査」)。
展望ある共生社会への道のりはまだまだ厳しい状況ですが、1993年3月8日に大阪市立大学にて、退職にあたって若い次世代に対して竹中さんが贈られたエールをご紹介します。竹中さんの言葉を胸に刻み、これからも歩んでまいりたいと存じます。
「とくに女性の場合にはいろいろな困難があると思いますけれども、ぜひ志を持ち続けていただきたいと思います。志を持ち続けるかぎり、おのずからいろいろなアンテナが張り巡らされて、いろんな知恵が浮かんでくるものだと思います。その覚悟をすれば、不思議に知恵が浮かぶものです。とくに若い人たちは、たしかに以前とは違って、叩けば門が開かれる、そういう時代にいます。私どもの若い頃とは違って、厳しいけれども進歩した状況の中に置かれています。しかし、それは決して何もしないでも自然に扉が開いてくるという状況ではないのです。だからこそ、そういう気持ちを持ち続けていただきたいと思うのです。
私はいつも言っているのですけれども、風当たりが強いかもしれないけれども、風当たりが強いのは、また向かい風を受けているのは、確かに前に進んでいるという証拠なのだ、ということです。そういう向かい風に向かって進んでいくということに、生きがいを感じられるそういう人生を、ひとりでも多くの女性に継いでもらいたいと思います。」
(『歳月は流水の如く』青丘文化社2003年より)